私は知りませんでした。インデックスファンドで長期投資という基本にして王道の投資方法しか知らなかった私は、「高配当株」投資という新しい世界を知りました。
高配当株とは
高配当株とは、配当利回り(1株当たり配当金÷株価)の高い株式を指します。つまり定期的な収入で資産を築いていく運用スタイルの株の事です。「定期的な不労所得」魔法の言葉ですね。
- 高配当株の魅力
- 高配当株の特徴
- 高配当株とインデックスファンド
- 気を付けろ高配当ETF
- 手数料負け対策は万全に
- まとめ
では詳しく見ていきましょう。
高配当株の魅力
高配当の企業とはどんな企業でしょうか?おそらく安定した収益基盤を持ち、株主に対しての高い利益還元の考えを持っている企業だとは思いませんか?そのような企業は経済情勢が悪化したとしても、安定した成果が期待できます。また「高配当株」好きの投資家は、株価が下がる場面でも株式を保有する傾向があります。その為、相場の下落に強いとの見方もあります。「高配当株投資」は、配当金を狙って株を買う投資法の為、株価の変動をあまり意識しなくてもいいのが嬉しいですね。長い目で見て資産が減っていなければ、理論上はずっと配当金を受け取れる事になります。インデックスファンドの長期投資と違って、定期的に配当金を受け取って活用出来るので、資産が増えていくのを実感しやすいのも魅力ですね。
あくまで株式投資です。株に絶対はありません。配当金が下がる可能性などのデメリットも理解して始めましょう。
高配当株の特徴
配当金が多いのは当然ですね。では株価が下がった場合はどうでしょう?高配当株の最大の特徴はここです、「株価が下がった場合には、配当利回りが上がります。」つまり株価が回復しやすい状況になるのです。これが「高配当株」投資家が株価が下がる場面でも株式を保有する傾向が多い理由です。下落相場に強いのも納得です。
ですがデメリットも当然あります。高配当株は当然「配当金額の高さ」に支えられています。つまり「配当金額」が業績不振で下がれば、大きく株価も下がります。「配当金額」が「株価」に直結しているわけです。また配当金の仕組みも理解しておきましょう。配当金は社内で蓄えられたお金を「株主に分配している」ので、会社の資金が流出しているとも取れます。当然、配当を出した分だけ企業価値は下がります。
高配当株とインデックスファンド
「高配当株」と「インデックス投資」ではどちらがいいのか?これは「自分の投資スタイル」によります。
「高配当株」は定期的な配当金を運用していくスタイルなので、「自由に使えるお金」が増えるイメージです。
「インデックス投資」は長期的な計画に基づいて運用していくスタイルなので、複利効果で「最終的に資産が増える」イメージです。
つまり、短期的な収入に関しては「高配当株」の方が多いが、長期的な収入は「インデックス投資」の方が多いという事です。どちらもメリット、デメリットがあるのでよく理解して運用しましょう。資産が潤沢にある方は、どちらもやってみていいと思います。目先のお金欲しいですよね。私は「高配当株」始めました。
気を付けろ高配当ETF
高配当ETFには信託報酬が高い、「地雷ETF」が数多くあります。「信託報酬が年0.1%以上」なら自分でポートフォリオを組んで運用した方が良いと思って下さい。特に国内のETFは信託報酬が高い傾向があります。有名な「日系高配当株50ETF」で年0.308%、「野村日本株高配当70連動型ETF」で年0.352%です。正直国内にこだわらないのであれば、海外の高配当ETFにした方が「信託報酬」は格段に低く抑えられます。手数料負けにならないようしっかりと対策をしていきましょう。
手数料負け対策は万全に
「高配当株投資」で配当金を受け取ると、必ず「20.315%の税金」がかかります。またETF投資を行なっている場合は「信託報酬」もかかります。このような手数料は事前に必ず確認しましょう。また「配当利回り」や、「配当性向」も調べておきましょう。
調べるのが手間、面倒臭いという方は「高配当株」には手を出さないでおきましょう。
まとめ
高配当株は、「配当利回りの高い」株式で、「定期的な収入で資産を築いていく運用スタイル」の株の事です。「下落相場に強い」といった特徴があります。分散投資をする場合は、長期運用も考えて「自分でポートフォリオを組みましょう。」「配当金に掛かる税金や手数料」を考えて運用しましょう。
高配当株は上手く運用できれば、「投資をしている実感が強く持てる楽しい投資方法」です。高配当という言葉だけで、「配当利回り」だけ見るのはやめましょう。メリットとデメリットは必ず両方あります。
最後まで記事を読んで頂き、ありがとうございました。少しでも皆様の力になれたなら幸いです。



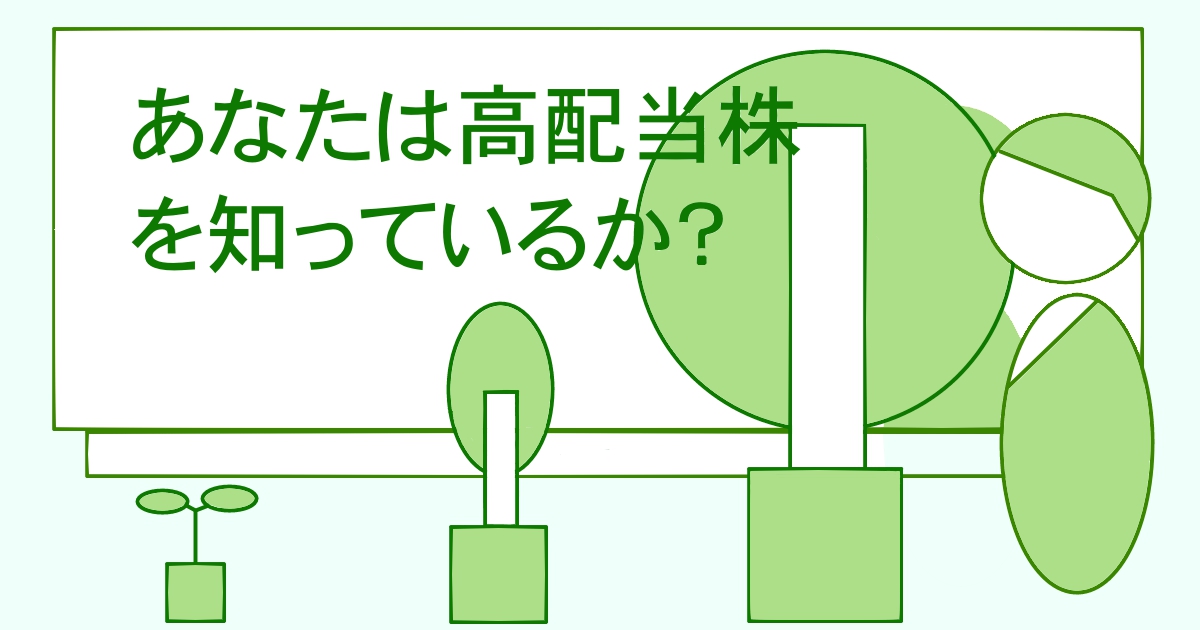
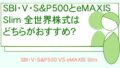

コメント